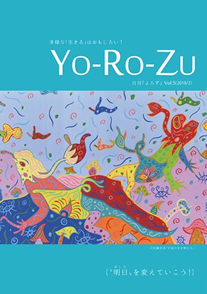[ 地下二階のお菓子屋です ]
教師ではない僕だから、先生とは違うことが伝えられることがあるはずだと思っている。同じように、みんなが誰かの「先生」になれる。そして、その発想がとても大事だと思う事例は日々スタッフと向き合う中で体験しているし、小学校から大学まで講演に行くたびに一層強く抱く実感でもある。
「エスコヤマ」の敷地内に小学生以下の子どもしか入れない「未来製作所」をオープンしたとき、一人の男の子を招待した。その少し前に講演に行った小学校の生徒だった。彼は先生たちの間では手に負えない生徒とされていた。しかし、僕の話には真剣に耳を傾けてくれて、終わった後に控室までやって来て、「NARUTO」のカードをくれた。先生ではできなかった何かを伝えることができたのだと思った。その後、少年の生活態度は落ち着いてきたと先生が教えてくれた。
僕がすごい語り手だからではない。僕が大事にしていることが彼に伝わったのだ。そういう関係性は、誰でもつくっていける。すべてを他人任せにしなくていい。
僕はコンクールの前に、審査員と積極的に会話する。直接の会話もあるし、そうでない「会話」もある。
あるとき、「インターナショナル・チョコレート・アワード」の審査員がお土産としてスモークの唐辛子など珍しい種類の唐辛子を持ってきてくれた。一つひとつ密封のビニール袋を開けながら、鼻を近づけた。お土産をくれた女性は、「水に戻して使うのよ」と言ったが、僕は、袋を開けた瞬間に香り立つそれぞれの違いに嗅覚を集中させていた。
そして、その中でも特に香りの良かったものを記憶し、その香りを新しいチョコレートに再現してアワードの出品作に加えた。僕に唐辛子をプレゼントしてくれた人には気づいてほしいと思っていたら、なんと“審査員のお気に入り”を意味する特別賞を受賞した。審査の状況は分からないが、少なくとも彼女は「ニヤリ」としながら口にしただろうと想像しながら、僕もニンマリとしてしまった。
そういう“いたずらっ子”のようなやり取りが好きなのだ。いただいたものに手を加えてお返しすると喜んでくれる、そんな楽しみ方が好きなのだ。しかもそれがたくさんの人にも喜ばれるものになれば、嬉しさは倍増する。どんな仕事にも、そんなちょっとした楽しみの忍び込ませ方はできる。
今回の「インターナショナル・チョコレート・アワード」には四十品を出品した。インターネットで調べると、三十六品が受賞ということが分かった。ところが、その中に、僕の自信作がなかった。「おかしい。事務局の手違いか、コンピュータの誤作動だ」と思った。ニューヨークの事務局に問い合わせると、案の定、コンピュータのミスだと判明した。それほど自信があったのだ。しかし、修正された記録を見ると、三十九品しか受賞していない。またもや「おかしい」と感じて問い合わせると、三十九品しか審査していないと言う。こちらからは出品記録を示して調べてもらったところ、一つだけ倉庫に眠っていたのだ。事務局はお詫びと共に、「来年、ぜひ出品してほしい」と要請してきた。僕が言いたいのは、自分自身の確かさが基準になっていれば、小さなことに違和感を持つことができるということだ。違和感もまた可能性を開いていく糸口になる。
ちなみに、そのアワードで一位を取ったのは、僕の予想通り、僕の作品だった。吉野川の青のりと柚子を使ったプラリネ。「青のりを使うなんて」と驚く審査員に対して、「ガラパゴス島の陸イグアナが海イグアナに変わった瞬間をイメージした。水の中に入っていけば、たくさんの素材があるはずだ、と思った瞬間、青のりが浮かんだ」とコメントを送った。
音楽プロデューサーの小林武史さんと話している最中、「地下二階のものづくり」という言い方が出てきて、とても興味深かった。小林さん曰く、ミスチルの桜井さんも、桑田佳祐さんも、小林さん自身も、僕も、「地下二階のものづくり人」なのだそうだ。
普通の人は、地上一階と地下一階の間を行き来してものづくりをする。これは、今の世の中のあり方が見えていて、そこに合わせようとして、結果的にオリジナリティのない似たものがあふれることになる。
一方、「地下二階」の住人は、地上で何が行われていても関係なく、青い空や心地いい風のイメージを大事にしながらものづくりをする。そう小林さんは解説してくれた。なるほど言いえて妙だなと感心した。
すでに書いたけれど、僕は世界一のトロフィーが欲しくてケーキやチョコレートを作っていない。その作ったもので誰かと誰かが新しい関係を築いたり、対話を生み出すきっかけになったり、自分自身を振り返るようになったり、くじけそうになっている人を激励したり、ということに役立つことが嬉しいだけなのだ。売れるための地上一階にいるわけではない。小林さんは、それを見抜いたのだと思う。
もし、僕が地上一階の人間なら、「情熱大陸」というテレビ番組のディレクターの最初の取材に満足していたかもしれない。そのディレクターは、朝から並んでくださっているたくさんのお客様の列ばかり撮って、「すごいですねー」を連発していた。それが何日も続いた。僕は、視聴者は行列を見せられても面白くないだろうし、何よりも僕自身が行列させて待たせていること自体がお店としては良くないことだと思っているので、さすがにその撮影には違和感があった。
そんな話を事あるごとにしながら二週間ほど経ったある日、僕にいつも同じことで注意されている若いスタッフがディレクターの目に留まった。そして、言われていることにじっと耳を傾けていると、どうやら若いスタッフの姿が自分のようだと気が付いた。そこから、彼の取材の内容に変化が表れたのだ。
ディレクターなのだから、もちろん自分を画面に登場させることはできない。その代わりにこの若いスタッフをカメラで追っていけば、自分を自分で見ることになる。そうしたら、自分を変えていけるのではないかと思ったそうなのだ。だから放送された「情熱大陸」は人材育成論的な内容が軸になっているのだが、それはそれでリアリティのあるものに仕上がった。
僕は、嬉しかった。そのディレクターが気づいてくれたことが。言ってみれば、彼自身が地上一階から地下二階にまで降りてこられたのだ。
「地下二階のものづくり」をしていると、必然的に人材育成に向かっていく。なぜなら、価値観を共有しなければ、チームや組織は運営できないからだ。ということは、人を育てることは価値観を育成していくことだとも言える。
そのために、僕はいろんな話をスタッフにするし、関わった人にはできるだけ伝えようと努力する。「お土産話」は聴くほうも楽しいし、それが、自分の家族や友人に広まっていくときに、「あのね、きょう、こんな話を聞いたんだ」と伝える主役が僕からその人へと変わる。自分が主体となって伝えようと思えば、目の前の人に伝わるように自分自身で工夫しなければならない。そこで伝える技術が磨かれていく。その伝える技術は、先のディレクターの例でも明らかなように、自分のこととしてとらえていくということだ。
「鳴門金時でお菓子を作ってみたいのですが」とある若いスタッフが言ってきた。「今はまだおいしい時期じゃない。この時期にいちばんおいしい鳴門金時を作ってる農家さんを調べてくれる? その一つのことが、次の自分のクオリティアップにつながるから」。そんな会話をする。また、あるときは、カメラマンと打ち合わせをする。
「味噌漬けにした燻製豆腐チーズっていうおいしいものを食べたから、それでチョコレートを作ろうと思う。そのイメージ写真を撮ってほしいんやけど」。カメラマンは赤味噌を用意してきたが、本来は、もろみに浸かったもの。「ほんまものを撮ってほしい。前から知っておく必要はないけれど、せっかく出逢ったことはちょっと深く勉強してみようや」。
自分が何もできないことを心配する必要はない。今、目の前のことを、今までと違うテンションで深堀りすれば、自然に、次から次へと自分のやるべきことが分かってくる。自分が変わっていくチャンスは、そうして無限に現れてきているのだ。そして、成長は、それに丁寧に関わっていく一歩一歩でしかあり得ない。
僕が関わる人たちすべてが、どんなかたちでもいいから一人前になってほしいと願い続けている。
月刊『YO-RO-ZU よろず』
ご購入をご希望の方は コチラ に
1.お名前、2.ご住所 3.電話番号 と
本文内に「 月刊よろず購入希望 」と
ご記入のうえご連絡ください。